| 主神 |
志那斗辨命(しなとべのみこと) |
| 配祀 |
日本武尊(やまとたけるのみこと) |
| |
天兒屋根命(あめのこやねのみこと) |
| |
塞三柱神(さえのみはしらのかみ) |
| |
大雀命(おおささぎのみこと:仁徳天皇) |
姉埼神社は、社伝によれば、人皇第十二代景行天皇四十年十一月、天皇の皇子日本武尊(やまとたけるのみこと)が御東征の時、走水の海で暴風雨に遭い
お妃の弟橘姫(おとたらばなひめ)の犠牲によって、無事上総の地に着かれ、ここ宮山台において、お妃を偲ぴ、風の神志那斗弁命(しなとべのみこと)を祀ったのがはじまりという。
その後景行天皇がこの地を訪れられて、日本武尊の霊を祀られ、更に人皇第十三代成務天皇五年九月、このあたりを支配していた上海上(かみつうなかみ)の国造(くにのみやつこ)の忍立化多比命(おしたてけたひのみこと)が天児屋根命(あめのこやねのみこと)と塞三柱神(さえのみはしらのかみ)を合祀し、又人皇第十七代履中天皇四年忍立化多比命五世の孫の忍兼命(おしかねのみこと)が大雀命(おおささぎのみこと:人皇第十六代仁徳天皇)を祀ったといわれる。
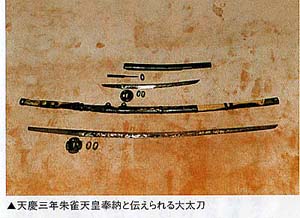 元慶元年(八七七)には神階も正五位上にまで進み天皇の勅願所ともなった。又『延喜式神名帳』にも、上総国の五社の一つとして載せられ、いわゆる式内社(しきないしゃ)として有名になった。
元慶元年(八七七)には神階も正五位上にまで進み天皇の勅願所ともなった。又『延喜式神名帳』にも、上総国の五社の一つとして載せられ、いわゆる式内社(しきないしゃ)として有名になった。
その後、天慶三年(九四〇)には、平将門追討の析願が寄せられ、神社へ刀剱一振りが奉納された。
ついで、源頼朝が房総の地から鎌倉への途次、杜前で馬ぞろえをして、武運長久を祈願したという。
更に関東が徳川氏の勢力下にはいるに及んで、慶長二年(一五九七)には松平参州侯が、慶長六年(一六〇一)には結城秀康が 共に社殿を造営したり、神馬(じんめ)を奉納したりした。なお
元和四年(一六一八)十一月には、この地の領主松平直政が社領三十五石を寄進し、蘆屋原新田五町六反二畝五歩をこれに充てた。
明治維新後、木更津県が誕生するに及んで、姉埼神社は県社となり、千葉県となっても引き継がれた。
 引用文献
引用文献
「姉埼神社参拝のしおり」 姉埼神社発行
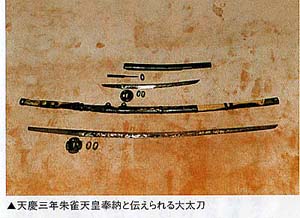 元慶元年(八七七)には神階も正五位上にまで進み天皇の勅願所ともなった。又『延喜式神名帳』にも、上総国の五社の一つとして載せられ、いわゆる式内社(しきないしゃ)として有名になった。
元慶元年(八七七)には神階も正五位上にまで進み天皇の勅願所ともなった。又『延喜式神名帳』にも、上総国の五社の一つとして載せられ、いわゆる式内社(しきないしゃ)として有名になった。![]() 引用文献
引用文献