簀立(すだて)
 汐が引いた海岸で大勢の人達が歓声をあげながら、魚を追っている。
汐が引いた海岸で大勢の人達が歓声をあげながら、魚を追っている。
子どもも大人も手に手に網を持って、「簀立」に取り残された魚をすくいあげている。
もちろん、取った魚はその場(船上)で調理し、新鮮な江戸前の魚を堪能できる。
こんな「簀立遊び」が姉崎の海で行われていました。
しかも、この「簀立」を湾内で最初に始めたのが姉崎の海であり、最も盛んであったのも姉崎の海であったという。
今でも木更津・金田海岸で昔ながらの手法で続けられています。
この「簀立」について紹介をします。
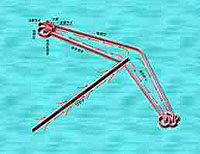 「簀立」は、遠浅の海岸の沖に網を張り、夜間網に入った魚を捕まえる定置網漁の一つです。
「簀立」は、遠浅の海岸の沖に網を張り、夜間網に入った魚を捕まえる定置網漁の一つです。
魚の通り道に左図のような定置網を設置してき、魚を網に沿って「みと」と呼ばれる網の終端に迷い込ませる仕掛けとなっている。
大正2年に旅館業を営んでいた稲毛氏が、印旛沼で行われていた『グレ漁』を姉崎の海に移したものが最初とされている。
印旛沼では孟宗竹を割ったものを縄であんだものを海底から建てる手法がとられていたが、これを丸い女竹に替えるなどの改良を加えた。
 大正の初め、姉崎に別荘をもっていた活動写真(映画)関係の雑誌『向島』の社長の岡崎氏が「簀立」を激賞し、映画俳優、仕事仲間などに宣伝したことにより広く世間に知られ、大正十四年には学習院の宮様方も訪れるほどになった。
大正の初め、姉崎に別荘をもっていた活動写真(映画)関係の雑誌『向島』の社長の岡崎氏が「簀立」を激賞し、映画俳優、仕事仲間などに宣伝したことにより広く世間に知られ、大正十四年には学習院の宮様方も訪れるほどになった。
容易に操業ができ、相当な利益が得られるため五井、袖ヶ浦、木更津、君津などにも広まった。
姉崎では純漁法としてより、簀立の設置場所を、干潮でも簀立海面が干上がらず泳いでいる魚がとれる場所にする、あらかじめとっておいた魚を生かしておく、「みと」を広くして大勢が入れるようにするなどの改良を重ね、観光に利用したことにより繁栄をもたらした。
これらが評判を呼び、昭和34年頃には姉崎地先には8統の「簀立」を数えるまでに発展したがあった。
獲物もタイ、カレイ、キス、アジ、エビ、カニ等々豊富であり、これらを直ぐに船上食べられることが評判を呼び、大いに繁盛した。
簀立の記録を残す「八反歩の碑」(藤根橋脇)
この繁栄も海が埋立てられるとともに消えていった。
 「房総展望」第13巻6号 昭和34年8月1日
「房総展望」第13巻6号 昭和34年8月1日
写真は「いちはら昔写真集」 市原市 昭和57年 より



 汐が引いた海岸で大勢の人達が歓声をあげながら、魚を追っている。
汐が引いた海岸で大勢の人達が歓声をあげながら、魚を追っている。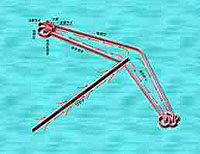 「簀立」は、遠浅の海岸の沖に網を張り、夜間網に入った魚を捕まえる定置網漁の一つです。
「簀立」は、遠浅の海岸の沖に網を張り、夜間網に入った魚を捕まえる定置網漁の一つです。 大正の初め、姉崎に別荘をもっていた活動写真(映画)関係の雑誌『向島』の社長の岡崎氏が「簀立」を激賞し、映画俳優、仕事仲間などに宣伝したことにより広く世間に知られ、大正十四年には学習院の宮様方も訪れるほどになった。
大正の初め、姉崎に別荘をもっていた活動写真(映画)関係の雑誌『向島』の社長の岡崎氏が「簀立」を激賞し、映画俳優、仕事仲間などに宣伝したことにより広く世間に知られ、大正十四年には学習院の宮様方も訪れるほどになった。

