著者:坂本 武夫
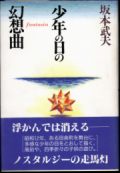 『かつての、よき姉崎の思い出』を残すのが当資料館の目的です。
『かつての、よき姉崎の思い出』を残すのが当資料館の目的です。この目的にピッタシの本がありました!!
昭和12年頃、研介少年の目を通して、当時の姉崎の暮らし振り、風習などを書いた『少年の日の幻想曲』(MBC21 発刊)がそれです。
幼馴染みで、喧嘩相手で、淡い恋心を抱いていた隣の「のこちゃん」との遊びと「のこちゃん」との別れまでを縦糸として、当時の中心街の町並み、そこに暮す人々の口が悪く、お世辞にも柄が良いとはいえないが、人の良い、助け合う人々の様子が生き生きと描かれています。
養老町生まれの坂本武夫氏が書かれたものです。
==>
昭和十二年。
蒸気機関車で、両国駅を発車した房総西線の下り列車は、千葉駅でスイッチバックし、姉ヶ崎駅に到着するまで二時間近くかかった。
進行右手に八反甫の田圃が広がり、彼方に連なる松並木を透して、東京湾の沖の波間にちらほら漁船の漂うさまを望み、左手に椀を二つ伏せたような二子塚と、遥かな丘陵群に一際小高い天神山と、姉崎神社のこんもりした森が見えてくると、列車は間もなく姉ヶ崎駅のプラットホームに滑り込む。
閑散とした駅前の、丸通前の道をしばらく行くと、千葉、木更津方面へと分岐する県道に出る。そのまま県道を突っ切ると、神社通りと呼ばれる細い通りに入り、姉崎神社に通ずる。
<==
この書き出しではじまる物語は、「喜久大本店」の研介少年が過ごした当時の姉崎の町並み、暮らし振り、遊び、風習等などが描かれています。
かたびて、ほーほんや、桃食って、じゃかぼこの子供の行事
姉崎神社の例祭、サーカス・相撲巡業・倶楽部での演芸、海水浴などの様子
戦争ごっこ、騎馬戦、ぴたんこ(めんこ)、玉っころ(ビー玉)、肝だめし・・・などの遊び
学校行事、町の出来事、お節介(?)な近所付き合い 等々
これらが、その現場に居合わせたような錯覚に陥るほど、生き生きと描かれています。
その一部を紹介します。
==>
蓮華の花園での兵隊ごっこも紙鉄砲を撃つ音、棒切れを叩き合う音が入り乱れた肉弾戦になった。
餓鬼大将格の焼芋屋の和ちゃんが、威張りくさって割り込んで来て、乃木大将の健ちゃんからサーベルを取り上げて、東郷元帥に変身した。着物の両剣先を裂いてぴたんこの勲章を付けていた。片方が楠木正成で、片方は後藤又兵衛だった。
「杉野は何処(いずこ)!杉野は何処!」
と、床屋の勇ちゃんが叫んだら、傘屋の彦ちゃんが杉野兵曹長になって、花園で溺れた真似をした。
花園の戦場には、旅順も、爾霊山(にれいざん)も、連合艦隊も、バルチック艦隊もへったくれもなかった。
戦場は一変して幕末になったりする。粉屋の利ちゃんが西郷隆盛になり、外交官の高ちゃんが月形半平太になった。自転車屋の幸ちゃんが桂小五郎で、小塚屋の実ちゃんが鞍馬天狗になった。長寅の信ちゃんが坂本竜馬になって、泥鰌屋の徹ちゃんが高杉晋作になって、池田屋で剣を交えたりすることになった。
小川の竹薮から、仕事師の久ちゃんの猿飛佐助と、鍛冶屋の政ちゃんの霧隠才蔵が跳び出して、坂本竜馬と高杉晋作に戦いを挑んだ。そこへ、どちらの助っ人(すけっと)か解らない蒟蒻屋の秀ちゃんの黄金バットが出て来て、花園は風雲混沌とした。
女の子の出番であった。のこちゃんと悦ちゃんと光ちゃんが従軍看護婦となり、頬を火照(ほて)らして負傷者を探し回った。
・・・・・
姉崎神社の祭礼の午前中に、「桃食って」という子供行事があった。桃食っては、かたびてのときと同じ顔ぶれであった。
集合場所も同じ稲荷神社の祠の前であった。
獅子舞いの狭い被いの中に何十人もの子供が潜りこんで、
桃食って こてらんね
お獅子が舞い込んだ
桃食って こてらんね
お獅子が舞い込んだ
獅子を迎えた家では、無病息災を願って獅子の歯で頭を噛んでもらった。噛んでもらうと、獅子の口の中にお捻りを入れた。西瓜、梨、桃を呉れる家もあった。
獅子舞にくっついていないと、お捻りの分け前に有り付けなかった。何十という小さい尻が被いの外にはみ出して、引っ張り回された。夏の真っ盛りで、獅子舞の中は茹蛸で一杯だった。茹蛸は目を眩(くら)ましていた。
<==
 私が、是非、読んで貰いたいと思うのは「エピローグ」です。
私が、是非、読んで貰いたいと思うのは「エピローグ」です。かつての、良き姉崎を見たあとでの「エピローグ」は、一層の共感を持ちました。
これを読むだけで高度成長時代の姉崎の変貌の様子が解ります。
少々長くなりますが、全文を紹介します。
右は著者の坂本 武夫氏
==> エピローグ
平成三年秋。
千葉駅、一部、両国駅から発車していた房総西線は内房線と改名され、経営は国有から株式会社に移管された。
機関車は、蒸気からディーゼルを経て、電気と改良され、軌道は複線となった。
普通電車は千葉駅、L特急・快速電車は東京駅が起点となった。一部の快速電車は横須賀線と提携で、横須賀・久里浜方面から木更津・君津までを東京駅経由で往復運転している。
千葉駅の移転に伴い、千葉駅でのスイッチバックは解消され、二時間あまり掛かっていた両国・姉ヶ崎間が、東京駅乗り入れから、東京・姉ヶ崎間の乗車時間は一時間あまりと短縮された。一日往復四十本にも満たなかった姉ヶ崎駅発着の列車は、快速を含めて百六十本にも増発されている。
風情のあった姉ヶ崎駅舎は、ステンドグラスを配した瀟洒な橋上駅に生まれ変わった。
車窓から展望された八反甫の田園風景も、海浜の松並木も、長閑な海の漂いも、痕跡もなく消え失せた。
二子塚は家並に隠れ、天神、明神の森周辺の優雅な丘陵は開発により疎らに刈り採られ、哀切の姿に変貌した。
詩情豊かだった八反甫の自然には、巨大なスーパーが客を呼び、ホテル、レストラン、そしてパチンコ、ゲームセンター、小キャバレーから赤提灯、小料理屋と、紅灯の賑わいが軒を連ねている。
浚渫(しゅんせん)で埋め立てられた、かっての海浜には、京葉工業地域の一環として日本でも屈指の化学・石油コンビナートが誘致され、コンビナートに群がる下請け町工場が犇(ひし)めいていた。
林立する高層の煙突から昇る煤煙と炎は、昼夜を分かたず天を焦がした。夜ともなると、コンビナートに点滅する灯火の煌めきは不夜城を醸し出し、恰も夜の観艦式を彷彿させた。
見えざる沖合いには二十万トンを越えるタンカーが停泊し、コンビナートに沿って新設された産業道路にはトラック、ダンプが我が物顔に咆哮し、数珠繋ぎに鈍走していた。
丘陵と、丘陵に連なる谷間は区画整理され、一丁目から七丁目までの団地は瞬く間に市街の形を整えた。家並を見下ろすマンション、社宅のモダンなビルが現代を装い、十階建の壮大な大学病院は連日患者で遅くまで混雑し、遠くから電車で押し掛ける繁盛振りであった。
団地は、在方の奥でも、空いている適当な土地さえあれば、何処にでも開発された。首都圏でも他県に比べて格安な土地は、若いサラリーマンのマイホームの夢を手頃に叶えさせ、東京方面への通勤も多くなり、マイカーの女房は、亭主を駅まで送り迎えした。
交通事故は県内でも一・二を競った。
土地暴騰で巨額の富を握った一部の成金は、一躍経営者の椅子に座った。
町はほかの町と合併し、二十六万の人口を抱える市に成長した。昭和十年代初期、六千そこそこであった町の人口は、同じ地域内だけでも五万人余と膨れあがった。
木造の荒屋(あばらや)だった小学校は、見違えるほど立派な鉄筋の校舎に生まれ変わった。小学校は有秋を加えて五校を数え、幼稚園、保育所、中学校が次々と増設され、後から高等学校も新設された。
ゴルフ場が雨後の竹の子のように生育し、フアンの間で、市はゴルフ銀座の名でも通っていた。
一方、半農半漁の生活の基盤は覆り、海苔を叩く音も跡絶えた。漁業権は莫大な保証金に替わったが、持ちつけぬ金はバブルに消え、工場に頼る中途半端な職に縋(すが)った。
山野は荒廃し、生計の覚束ない農家は伝来の農地を宅地に転用して売却し、頼りにならない田畑は荒れるに任せた。
小川のせせらぎは溝川に転じ、メタンガスを放って蓋を掛けられた。
蓮華の花園にマンションが建ち、ホタルの夢幻の光りも、昔日の彼方に消滅した。
野鳥や昆虫類は、強者を残し奥地へ移動した。
神代の郷愁を誘った姉崎神社も不始末から焼失し、金ピカの社殿に生まれ変わった。
妙経寺の赤松は伐採され、寺山の空地と共に小住宅が肩を寄せ合う場所となった。
研介たちの自然の楽園は、昔語りに埋没され、代わって企業のプールで芋を洗い、高価な標本で昆虫の生前を偲び、塾と、テレビと、ファミコンで一日を過ごすようになった。
混沌とした思想も生まれた。怪し気な新興宗教が乱立し、現代の道鏡も富を追い、信者は遮眼革(しゃがんかく)をつけて教祖の後に従った。
天皇は神から人間に帰った。消化されない民主主義は利己主義を生み、言論の自由は自己の主張に自惚れた。家族制度は崩壊し、親子の隔絶は拡がり、人は宛(さなが)ら目標を失い、繁栄に伴う虚飾の栄華に現(うつつ)を追うかの如くであった。
やがて東京湾横断道路が完成される。果たして発展の中に、何が生まれ、何が失われていくのだろう。夢うたかたの中に過去を歩んで来たが、更なる前途を思うとき、不安に惑わざるを得ない。
この年、新しい市長が二十六万人の支持を得て誕生した。新市長の抱負もまた大であろう。産業開発と環境保全という板挟みの中で、市政三十年を迎えようとする、広範な地域社会のコンパスを如何に舵取りするか、市長の行政手腕に頼るところである。
養老町の名も消え、傘屋、蹄鉄屋、泥鰌屋、玉子屋、鋳掛屋、勇ちゃんの床屋も消えた。
研介は、菓子屋の暖簾を継ぐこともなく、六十五歳の晩秋を迎えた。
<==
 引用文献
引用文献『少年の日の幻想曲』 坂本武夫 編著 平成4年 MBC21 発刊