
椎津城の歴史は北条氏、里見氏の関東における覇権争いの歴史であった。
戦国時代、上杉謙信と武田信玄が川中島で決戦をしていたとき、関東では小田原北条氏と、安房里見氏がともに関東の覇者にならんとしてその勢力を拡大していった。 そして両者は上総・下総で激突し、椎津城もその荒波に揉まれ北条方・里見方との間を揺れ動いた。
この争いは国府台(こうのだい)の戦いで北条氏の勝利で決着がつき、椎津城は北条方のものとなった。 しかしその北条氏も豊臣秀吉に攻め滅ぼされ、椎津城も秀吉より関東を与えられた徳川軍に攻め落とされその役目を終えた。
『写真は城山にたつ、椎津城跡の碑』
戦国時代、上杉謙信と武田信玄が川中島で決戦をしていたとき、関東では小田原北条氏と、安房里見氏がともに関東の覇者にならんとしてその勢力を拡大していった。 そして両者は上総・下総で激突し、椎津城もその荒波に揉まれ北条方・里見方との間を揺れ動いた。
この争いは国府台(こうのだい)の戦いで北条氏の勝利で決着がつき、椎津城は北条方のものとなった。 しかしその北条氏も豊臣秀吉に攻め滅ぼされ、椎津城も秀吉より関東を与えられた徳川軍に攻め落とされその役目を終えた。
『写真は城山にたつ、椎津城跡の碑』
椎津城
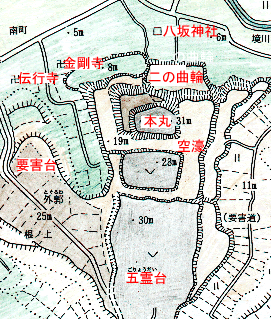 椎津城は「城山」と呼ば高台(海抜30m)が中心部にあたり本丸があった場所である。 本丸は、古墳を利用して作ったことが昭和46年の発掘調査で判明している。
椎津城は「城山」と呼ば高台(海抜30m)が中心部にあたり本丸があった場所である。 本丸は、古墳を利用して作ったことが昭和46年の発掘調査で判明している。
本丸下南側の内堀は空濠で、薬研枡形掘り(やげんますがたほり)という掘り方になっている。 (上幅が14m、深さ4.5mあり、この掘りに落ちると人の高さ迄が角型になっており、その上は薬研のようにだんだん上幅が広っがており、地面のうえまではなかなか上がれない。)
本丸の北側中腹に二の曲輪、さらにその下の八坂神社、金剛寺東がある一段高い平場が三の曲輪であり、この北側には房州往還道がとおりその両脇には集落があった。 この向こうは海岸であった。
背後の台地にも空堀で区切られた曲輪をもち、その南の五霊台(ごりょうだい)も空堀がめぐらされここまをが城域として取り込んでいた。 郭内台地は戦ともなれば兵員を収容する寝小屋(根小屋)になる絶好な広場である。
 南西側は要害台(げえでえ)と呼び、行伝寺上は舌状の外郭が張り出して、城郭としての堅固さを一層誇っている。 西南側の台地下は当時は湿地帯であり菖蒲沼水田もあった。 市街地を隔てた西側一帯は海に面した要害線であった。
南西側は要害台(げえでえ)と呼び、行伝寺上は舌状の外郭が張り出して、城郭としての堅固さを一層誇っている。 西南側の台地下は当時は湿地帯であり菖蒲沼水田もあった。 市街地を隔てた西側一帯は海に面した要害線であった。
『写真は要害台(手前)から谷をへだてて城山を望む』
 東側は谷間を隔てて向こう台地につながり、その北端の高所が勝望山(正坊山)であり、本城を守るための外城として、 またここは敵情を望見するには絶好の場所でもあった。 勝望山の東裾は広く、江戸時代の末には鶴巻藩の陣屋が置かれたところで今は姉崎小学校になっている。
東側は谷間を隔てて向こう台地につながり、その北端の高所が勝望山(正坊山)であり、本城を守るための外城として、 またここは敵情を望見するには絶好の場所でもあった。 勝望山の東裾は広く、江戸時代の末には鶴巻藩の陣屋が置かれたところで今は姉崎小学校になっている。
『写真は勝望山(手前)と城山(後方)』
城地の東側および北部一帯には境川が取り巻いて流れており、台地とともに一大城郭を構成していた。
また境川を越えた東側の砂子(いさご)、北側の川崎にはそれぞれ稲荷様があり、椎津城の守り神として祀られていた。
この稲荷様は規模は小さくなっているものの現在も祀られている。

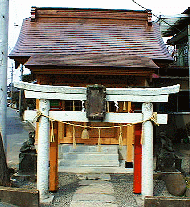
『写真は砂子(左)と川崎のお稲荷様』
 参考文献
参考文献
市原教育委員会 「市原のあゆみ」
鈴木 亨著「日本合戦史100話」 中央公論社
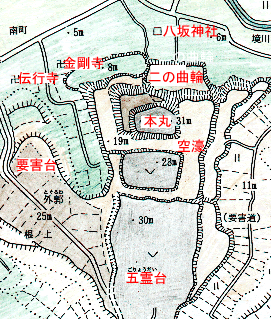 椎津城は「城山」と呼ば高台(海抜30m)が中心部にあたり本丸があった場所である。 本丸は、古墳を利用して作ったことが昭和46年の発掘調査で判明している。
椎津城は「城山」と呼ば高台(海抜30m)が中心部にあたり本丸があった場所である。 本丸は、古墳を利用して作ったことが昭和46年の発掘調査で判明している。本丸下南側の内堀は空濠で、薬研枡形掘り(やげんますがたほり)という掘り方になっている。 (上幅が14m、深さ4.5mあり、この掘りに落ちると人の高さ迄が角型になっており、その上は薬研のようにだんだん上幅が広っがており、地面のうえまではなかなか上がれない。)
本丸の北側中腹に二の曲輪、さらにその下の八坂神社、金剛寺東がある一段高い平場が三の曲輪であり、この北側には房州往還道がとおりその両脇には集落があった。 この向こうは海岸であった。
背後の台地にも空堀で区切られた曲輪をもち、その南の五霊台(ごりょうだい)も空堀がめぐらされここまをが城域として取り込んでいた。 郭内台地は戦ともなれば兵員を収容する寝小屋(根小屋)になる絶好な広場である。
 南西側は要害台(げえでえ)と呼び、行伝寺上は舌状の外郭が張り出して、城郭としての堅固さを一層誇っている。 西南側の台地下は当時は湿地帯であり菖蒲沼水田もあった。 市街地を隔てた西側一帯は海に面した要害線であった。
南西側は要害台(げえでえ)と呼び、行伝寺上は舌状の外郭が張り出して、城郭としての堅固さを一層誇っている。 西南側の台地下は当時は湿地帯であり菖蒲沼水田もあった。 市街地を隔てた西側一帯は海に面した要害線であった。『写真は要害台(手前)から谷をへだてて城山を望む』
 東側は谷間を隔てて向こう台地につながり、その北端の高所が勝望山(正坊山)であり、本城を守るための外城として、 またここは敵情を望見するには絶好の場所でもあった。 勝望山の東裾は広く、江戸時代の末には鶴巻藩の陣屋が置かれたところで今は姉崎小学校になっている。
東側は谷間を隔てて向こう台地につながり、その北端の高所が勝望山(正坊山)であり、本城を守るための外城として、 またここは敵情を望見するには絶好の場所でもあった。 勝望山の東裾は広く、江戸時代の末には鶴巻藩の陣屋が置かれたところで今は姉崎小学校になっている。『写真は勝望山(手前)と城山(後方)』
城地の東側および北部一帯には境川が取り巻いて流れており、台地とともに一大城郭を構成していた。
また境川を越えた東側の砂子(いさご)、北側の川崎にはそれぞれ稲荷様があり、椎津城の守り神として祀られていた。
この稲荷様は規模は小さくなっているものの現在も祀られている。

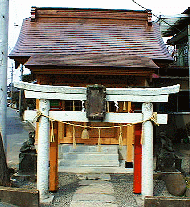
『写真は砂子(左)と川崎のお稲荷様』
康正2年(1456)甲斐武田家の流れをくむ武田信長、信高親子が古河公方足利成氏の命を受けて真里谷城、庁南城を築く。 この直後に支城として椎津城が作られた。 真里谷城3代城主信保の跡目相続争いが椎津城信隆・真里谷城主信応の間に起こり信隆は北条氏に、信応は小弓公方足利義明と義明を担ぐ里見氏にそれぞれ支援を求めた。
天文6年(1537)足利義明は里見義堯と共に椎津城を攻め、信隆は北条氏を頼り武蔵国の金沢に落ち延びた。
天文7年(1538)北条方と足利義明を担ぐ里見義尭が房州・国府台で戦い(千葉県市川市:矢切りの渡し近く 国府台前役)で、義明自らが戦場に押し出し首をとられるなど里見軍が大敗した。 義尭は安房まで逃げ帰り、北条方は房州境まで追撃した。このとき椎津城は北条方に落ち、信隆は城主に帰り咲いた。
国府台の敗戦の後、里見義尭は国の強化に努めその勢力を回復して上総の国の大半を侵略した。 一方北条方も武田信隆のあとを継いだ椎津城主信政と密約を交わし、里見家を一気に滅ぼそうと企てた。
国府台の敗戦の後、里見義尭は国の強化に努めその勢力を回復して上総の国の大半を侵略した。 一方北条方も武田信隆のあとを継いだ椎津城主信政と密約を交わし、里見家を一気に滅ぼそうと企てた。
天文21年(1552)北条との密約に激怒した里見義尭は、万木城土岐頼定、大多喜城正木大膳亮時茂らを率いて椎津城を攻めた。 椎津城の武田信政は小田原から加勢を得てこれを迎え討った。 信政は城から5町の距離にある山(勝望山?)を楯に戦い激戦となったが、椎津勢が大敗するところとなり信政は自害して果てた。 義尭は、重臣の木曾左馬充に椎津城を守らせた。 このとき上総のほとんどは里見氏の手中に帰した。
永禄7年(1564)再び北条氏家、氏政親子と、里見義弘が国府台で戦った。(国府台後役) またも里見軍は敗れ、北条方は余勢をかって椎津城など里見方の支城を落とし久留里と佐貫の両城を残して上総西北部を制覇した。 このとき椎津城には白旗六郎を城番とした。
天正18年(1590)豊臣秀吉は小田原を攻め、北条氏を滅亡させた。このとき秀吉は自ら小田原城包囲戦をおこなう一方、別部隊には関東にある北条の支城を攻めさせことごとく攻略していった。 椎津城は豊臣方浅野長政に攻められ落城した。
城主の白旗六郎は白塚村まで逃げたがこの地で討ち死にした。 白塚村には六郎の亡骸を埋葬した所と言われている「塩煮塚」(正人塚が転訛)があったが、明治44年の鉄道建設工事で消滅した。
これを最後に椎津城は歴史から消えていった。
城主の白旗六郎は白塚村まで逃げたがこの地で討ち死にした。 白塚村には六郎の亡骸を埋葬した所と言われている「塩煮塚」(正人塚が転訛)があったが、明治44年の鉄道建設工事で消滅した。
これを最後に椎津城は歴史から消えていった。
=>国府台の合戦、里見家の詳細はリンクから「南総里見之館」へ
 参考文献
参考文献市原教育委員会 「市原のあゆみ」
鈴木 亨著「日本合戦史100話」 中央公論社