また、昭和になって直木賞小説の題材となった男。
この姉崎で一番の有名人をご存じでしょうか。
この人の名は「市兵衛」と言います。
昭和16年第12回直木賞を受賞した村上元三著「上総風土記」(昭和15年/大衆文芸 発表)より市兵衛の奮闘を紹介します。
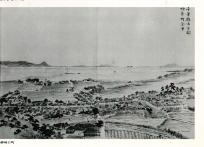
徳川5代将軍綱吉の悪名高き「生類憐れみの令(元禄四年)」が発布されているさなかの元禄八年の出来事が発端であった。
市原郡で公儀の許しを得て行った鹿狩りで、誤って「お竹」という婦人を撃ち殺すという事故が起きた。(お竹騒動)
犬一匹殺しても厳罰のこの時期、まして人を殺してはどの様なおとがめがあるか、関係する姉崎、片又木、立野、不入斗、深城、天羽田、長谷川の七ヶ村の名主は相談の結果、この件は公儀に届けないこととした。
しかし、これが公儀の知るところとなり7名の名主は伊豆の大島へ島流し、土地家屋は没収となった。このため名主の奉公人達は暇をだされ離れていった。 (写真は明治初期の姉崎)
そのなかで、姉崎村の名主・次郎兵衛の下僕・市兵衛は、私財をなげうって養老川から水を引いたり、蜜柑の作付け、養蚕の奨励を行った次郎兵衛を深く尊敬しており、親子代々世話になった名主さまに恩返しするのはこのときと決心をしました。
次郎兵衛の残された家族は年老いた父、女房、そして島流しの後に生れた万五郎の3人でした。 ただでさえ貧しい市兵衛にとって彼らを養っていく事とは、並大抵なことではありません。
小作の仕事を終えてから、養老川の石運び、姉崎浜での漁師の手伝い等々、女房の「おのぶ」とともに死にもの狂いで働きました。 あげくには、一人娘の「お清」まで子守奉公に出し、その前借り金で家族のために小屋を建てる事までやりました。
そんな市兵衛夫婦を周りのものたちは「あの夫婦は気が触れた」と敬遠する有様でした。
また一方で市兵衛は、五井の代官所へ通い「自分を身代わりに島に送り、主人を返して欲しい」と哀訴し続けました。 代官はもてあまし、「江戸の勘定奉行の所へ行け」と告げました。 まさか江戸までは行かずに、あきらめるだろうとの思っての事です。
しかし、主人を救いたい一心の市兵衛とっては、江戸までの15里の道も試練の一つに過ぎませんでした。
姉崎を夜立ち、寝ずに歩き続け江戸で勘定奉行への訴えをして(いつも門前払いでしたが)、その夜に姉崎へ戻るという事を毎月、欠かさずに行いました。 万五郎が大きくなると彼を背におぶい、江戸までの往復をくりかえしました。
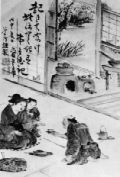 さらに市兵衛にとって気がかりがありました。それは次郎兵衛が尽力した蜜柑の栽培、養蚕を誰もが見向きもしなくなり、さびれていった事でした。 このままでは主人の努力が無駄になると思い、空き地を借り受けて蜜柑の苗を植え、また桑を栽培して蚕を育てことを始めました。
さらに市兵衛にとって気がかりがありました。それは次郎兵衛が尽力した蜜柑の栽培、養蚕を誰もが見向きもしなくなり、さびれていった事でした。 このままでは主人の努力が無駄になると思い、空き地を借り受けて蜜柑の苗を植え、また桑を栽培して蚕を育てことを始めました。
初めは見て見ぬ振りをしていた村人も段々に市兵衛の下に通うようになり、市兵衛の手ほどきを受けてこれらが村中に広まりました。 このおかげで、凶作のときも姉崎村では餓死者を出さずに済み、市兵衛は姉崎村の中心的な人物となりました。
しかし、市兵衛の江戸への哀訴は続けられました。 すでに次郎兵衛が島流しされてから9年の歳月が流れていました。
やがて時の勘定奉行 萩原近江守の耳に市兵衛のことが入りました。近江守は心を動かされ、市兵衛に出頭を命じました。
市兵衛は「きっと旦那さまがご赦免になるのだ」と小躍りして喜びました。
一方で、主人の身代わりに大島へ行くことになるのだと覚悟をきめ、女房の「おのぶ」に今生での分かれを告げ、娘のお清にもそれとなく名残を告げ、万五郎を連れて近江守のもとに出頭しました。
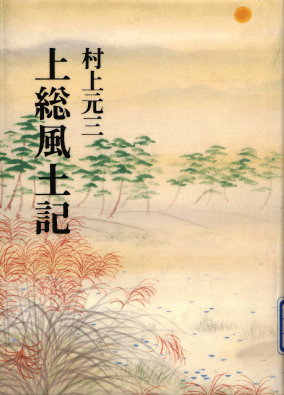 これからがこの小説のクライマックスです。
これからがこの小説のクライマックスです。
ここは原文のまま紹介しましょう。
(「上総風土記」村上元三著 六興出版)
だが、市兵衛が江戸へついて、近江守から伝えられたのは、次郎兵衛の放免ではなかった。
「其方の今までの志に賞で、姉ヶ崎村の田畑六町歩、金子十両を褒美として差つかわさる」
庭先でそれを聞いた市兵衛は近江守を黙って仰ぎ見た。
不服そうな眼色だった。
「お受けいたしかねます。」
「いやか」
「はい。御褒美など頂いては、始めは主人の為にお願い致しながら、後には自分の為にした事のようになります。」
「其方が受けねば、それなる次郎兵衛の子万五郎へ与える」
「有難う存じまする。しかし主人次郎兵衛をお許しくださりませぬでござりますか」
「この上、勝手を申すな」
「御奉行様」
市兵衛は庭先へにじり寄った。必死な気魄が、顔に溢れている。
「わしは生きて姉ヶ崎へ戻らぬ覚悟をしておりまする。主人に代わって、わしを島へお流しくださりませ。主人次郎兵衛を、姉ヶ崎へお戻し下さりませ。お願い、お願いでござります」
じっと市兵衛を見ていた近江守は、怖い顔をした。
「掟は曲げられぬ」
「お願いでございます」
「ならぬ、其方、いま次郎兵衛に代わって、姉ヶ崎村にとり、無くては叶わぬ人間じゃ。それを思えば、其方の命、身体、自侭には捨てられぬぞ」
「違いまする、わしの今まで致しました事は自分の事を考えてではございません。あるじ次郎兵衛に教えられた通り、また次郎兵衛に代わって、致しましたのでございます」
「それだからこそ、姉ヶ崎村にあって、いつまでも主の志を継げ」
「御奉行様はお分かり下さりませぬ、わしは」
「ならぬ、立帰れ」
いい捨てて、近江守は奥へ入った。
「御奉行様、お願い,お願い」
なお、ないて叫ぶ市兵衛を、下役の者たちはなだめすかし、表へ連れ出した。
だが、その日が暮れてからも、夜中になってからも、市兵衛は門前に座り、門扉に向かって主への身代わりを嘆願し続けた。
それを下役から伝え聞いた近江守は、
「困った奴」
溜息をついたが、眼は微笑していた。
そして翌宝永三年の春。
次郎兵衛はじめ市原郡七ケ村の元名主達は、とうとう許されて、十一年目に、伊豆の大島から故郷に戻ってきた。それには荻原近江守の奔走と尽力があった。
市兵衛は、主の次郎兵衛を、村外れの道まで迎え出た。市兵衛は四十三才、次郎兵衛は四十五才になっていた。
「市兵衛」
次郎兵衛は呼んだきり、両手を顔へ押し当てた。その前に市兵衛は、両手をついて座り、布子の肩を震わして泣いていた。
次郎兵衛は、この十一年間の市兵衛の苦労を、近江守から聞かされていた。自分が召捕りになってから暇をとって去ったとばかり思っていた市兵衛が今こうして自分を迎えてくれているのであった。
姉ヶ崎村の畑地には、蜜柑や桑の木が、明るい陽ざしを浴びて、青々と茂っていた。どの家からも、機の音が聞こえていた。次郎兵衛が居たときよりも、はるかに活気があった。
 中略
中略
宝井其角に、次のような句がある。
---起きて聞けこのほととぎす市兵衛記---
=終わり=
(姉崎・妙経寺にある其角の句碑)
=>この小説を読んで大変感動しました。
皆さんにも是非読んでいただきたい。
この本は絶版ですが、市原中央図書館で借りられます。
 参考文献
参考文献「上総風土記」村上元三著 六興出版 昭和58年
写真は「いちはら昔写真集」市原市役所 広報課