勝間
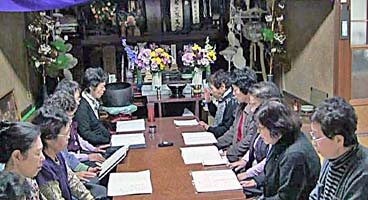
| 地区名 | 念 佛 | 備考 |
| 不入斗 | 光明、親の讃、早川、葉カケ、花陀山、面白や、行屋、十三佛、弥陀の讃、釈迦讃、 薬師讃、七夕、六道、さらさら、新家、庚讃、石たて、観音讃 |
YouTubeに動画登録済 |
| 平田 | 光明遍照・立花・差し上げ、十九夜念佛 | |
| 西青柳 | ほどまで、四十九日、先祖、百ケ日、石たて、彼岸念佛、寺念仏、塔婆念佛、 受取り、十五夜念佛、届念佛、善光寺、三日、七日、三十日、花陀山 |
|
| 宮原 | 子安様①、子安様② | |
| 松ケ島 | 子安様、十九夜、堂ぼめ、だんなぼめ、茶ぼめ、差しあげ | |
| 勝間 | 懺悔文、光明遍照、弥陀頼む、えそげた、あげ念佛、我親、子供念佛、年忌念佛、 六道、御盆念佛、彼岸念佛、行屋念佛、墓石念佛、 和讃⇒弘法大師和讃、弘法大師、興教大師、善光寺、龍性院、満光院、地蔵院、 法泉寺、神照寺、笠森寺、十三佛、大師様 |
注:念仏の多くは「ひらがな」で書かれているため、上段にひらがなを太字で、下段に当館で宛てた漢字を表示した。
念仏原本に漢字があるものはこれを下段に表示した。原本の漢字が誤りと思われるものはカッコ書きで訂正文字をっ追記した。
不入斗
| 『こうみょう』 『光明』 こうみょうへんじょう じゅっぽうせかい 光明遍照 十方世界 ねんぶつしゅじょう せっしゃふしゃ 念仏衆生 節射普射 みだたのむ みだたのむ 弥陀頼む 弥陀頼む らいしょうのことを みだたのむ 来世の事を 弥陀頼む こくらくじょうどは とにもかくにも 極楽浄土は 兎にも角にも なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 みだたのむ みだたのむ 弥陀頼む 弥陀頼む ひとはあまよの つきなれど 人は天世の 月なれど くもははれねども にしへよこそ 雲は晴れねども 西へよこそ なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 |
『おやのさん』 『親の讃』 あさゆうみあげし わがおやの 朝夕見上げし 我親の ししてめいどへ まいるとき 死して冥土へ 参る時 のべのおくりも ゆめじさえ 野辺の送りも 夢路さえ ひろいのはらも せまくなる 広い野原も 狭くなる せんだのたきぎを つみかけて 千駄の薪を 積みかけて のべかやまかで かそうする 野辺か山かで 火葬する いちにちににちは けむりたつ 一日二日は 煙り立つ さんにちさんやと もうすとき 三日三夜と 燃うす時 こつをひろいし はいをよせ 骨を拾いし 灰を寄せ ゆうひかがやく そのてらへ 夕日輝く その寺へ こつをおさめし いはいたて 骨を納めし 位牌立て おやのためとて こうをもりて 親の為とて 香を盛もりて こうのけむりが はなとたつ 香の煙りが 華と立つ なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 そこまでや そこまでや そこまでや そこまでや よそとおもいし はすのはに よそとおもいし 蓮の葉に ことしてにとる みそはぎを 今年手に取る ミソハギヲ たむけもうすよ わがおやに 手向け申すよ 我親に なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 <不入斗> |
| 『はかけ』 『葉かけ』 ただいまもうした おねんぶつは 只今申した お念佛は こがねのおはちを つみあげて 黄金の御鉢を 積みあげて ほとけのまえに さしあげて 佛の前へ 差し上げて おいたとまおまもうして いざかえる お暇申して いざ帰る なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 |
|
| 『はやかわ』 『早川』 はやかわの はやかわの 早川の 早川の< つながぬふねの とまるとも 繋がぬ船の 止まるとも しするいのちは もはやとまらぬ 死する命は もはや止まらぬ なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 いそげひと いそげひと 急げ人 急げ人 みのりのふねの いでむまに 実りの船の 出でぬ間に のりおくれれば たれかわたさん 乗り遅れゝば 誰か渡さん なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 |
『はなださん』 『花陀山』 きみょうちょうらい はなださん 帰命頂禮 花陀山 はなのようなる こをもちて 花の様なる 子を持ちて むじょうのかぜに さそわれて 無常の風に 誘われて あまりわがこの こいしさに 余り我子の 恋いしさに はなだのてらへ まいりきて 花陀の寺へ 参り来て てらのしょえんに こしをかけ 寺の所縁に 腰を掛け はなをつくづく ながむれば 花をつくづく 眺むれば ひらきしはなは ちりもせず 開きし花は 散りもせず つぼみしはなの ちるごとく 蕾し花の 散るごとく げにやわがこも あのごとく げにや我子も あのごとく とりはふるすへ かえれども 鳥は古巣へ 帰れども なぜかわがこは かえりゃせぬ 何故か我子は 帰りゃせぬ なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 <不入斗> |
| 『ぎょうや』 『行屋』 おぎょうやでは おぎょうやでは お行屋では お行屋では さてもみごとな おぎょうや さても見な お行屋 まえにぼんてん おたてやる 前に梵天 お立てやる うちにはななえの しめをはり 内には七重の 注連を張り ひだりには ひだりには 左には 左には しせいぼさつが おたちやる 勢至菩薩が お立ちやる みぎりには みぎりには 右には 右には かんのんぼさつが おたちやる 観音菩薩が お立ちやる なかにはだいにち ゆりのざに 中には大日 ゆりの座に さてもみごとな おぎょうや さても見事な お行屋 |
『おもしろや』 『面白や』 おもしろや おもしろや 面白や 面白や うかのさかもり おもしろや うかの酒盛リ 面白や しろがねちょうしに こがねさかづき 白金銚子に 黄金盃 なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 おしゃくには おしゃくには お酌には お酌には びしゃもんべんてん おたちやる 毘沙門弁天 お立ちやる まいるかたには うかとだいこく 舞いる方には うかと大黒 なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 <不入斗> |
| 『みだのさん』 『弥陀の讃』 そもそもみだの せいがんに そもそも弥陀の 誓願に しょぶつのなかに すぐれたまう 諸佛の中に 優れ給う ほうぞうびくの むかしより 法蔵比丘の 昔より しじゅうはちがん じょうじゅして 四十八願 成就して によけこうにょらいと あらわれて によけこう如来と 現れて いちねんみだの くりきにて 一念弥陀の 功力にて かならずらいしょう ひつじょうして 必ず来世 必生して じゅあくごじゃくの つみにけり 十悪五逆の 罪にけり このねんぶつの くりきにて この念佛の 功力にて にせいあんらくと たのみあげ 二世安楽と 頼みあげ しるもしらぬも おしなべて 知るも知らぬも 押並べて すくはせたまえ みだにょらい 救はせ給え 弥陀如来 なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 |
『やくしさん』 『薬師讃』 きみょうちょうらい なむやくし 帰命頂禮 南無薬師 やくしようかに まいりきては 薬師八日に 参り来ては じゅうにのいとを てにもちて 十二の糸を 手に持ちて じゅうにちょうの ゆみをはり 十二丁の 弓を張り くでんのわきなる かぎかねを くでんのわきなる かぎかねを かけつきねんに もうしべし 掛けつ祈念に 申すべし これもやくしの ちかいなり これも薬師の 誓なり やくしのうえとて かたにかけ 薬師の上とて 肩に掛け それもやくしの ちかいなり それも薬師の 誓なり なむやくしの じゅうにじん 南無薬師の 十二神 しるもしらぬも おしなべて 知るも知らぬも 押並べて すくはせたまえわ なむやくし 救はせ給え 南無薬師 なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 <不入斗> |
| 『かんのんさん』 『観音讃』 あかつきごやに にしみれば 暁ごやに 西見れば しほうしくんの くもたちて 四方紫薫の 雲立ちて なかにはみりの かんのんの 中にはによりの 観音の じひなほとけに ましせんば 慈悲な佛に ましせんば せかいのにょにんの みがわりに 世界の女人の 身代わりに ひろさがはちまん よじんなり 広さが八万 余旬なり ふかさはちまん よじんなり 深さ八万 余旬なり ちなるいけにぞ おたちやる 血なる池にぞ お立ちやる かたちやつれて おたちやる 形やつれて お立ちやる まよいのにょにんは それしらず 迷いの女人は それ知らず ひかりおがまぬ あわれさよ 光を拝まぬ 哀れさよ ひかりおがみし ひとはまた 光を拝みし 人はまた ななえのひざを やえにおり 七重の膝を 八重に折り はちすのこうべを ちにつけて はちすの頭を 地に付けて とうのれんげを さしあげて 塔の蓮華を 差し上げて みだかんのんと ねんずべし 弥陀観音と 念ずべし ごしょうしょしょとんじょう ごしょうしょしょとんじょう じょなんぼう じょなんぼう ふだらくせかいなり 補陀落世界なり はんにゃのふねに のりうつり 般若の船に 乗り移り ちはやはんにゃの かぜふかば 千早般若の 風吹かば すぐにじょうどに まいるべし 直ぐに浄土に 参るべし なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 |
『しゃかさん』 『釈迦讃』 おしゃかはつきひの お子なれど 御釈迦は月日の お子なれど ななつでがく なるべし 七(ナナ)つで覚 なるべし じゅうごでせんぶつを およみあげ 十五で千佛を お読み上げ しちじゅうごにんの でしをもち 七十五人の 弟子を持ち ろくじゅうにとめと もうすとき 六十二とめと 申すとき ごにゅうめつ なさるべし 御入滅 なさるべし しちじゅうごにんのなな でしたちが 七十五人の 弟子達が みなすいしょうの ずずをもち 皆水晶の 数珠を持ち ねりあるとの ごせいがん ねりあるとの 御請願 なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 <不入斗> |
| 『かのえさん』 『庚讃』 かのえおまえを ながむれば 庚お前を 眺むれば ろくじのはなが さきみだれ 六字の花が 咲き乱れ はなはおりたし きはたかし 花は折りたし 木は高し はなれがたきの おまえばな 離れ難きの おまえ花 なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 <不入斗> |
|
| 『じゅうさんぶつ』 『十三佛』 いちにおふどう ににおしゃか 一にお不動 二にお釈迦 さんにおもんじゅ しにふげん 三にお文殊 四に普賢 ごにはじぞう ろくみろく 五にはお地蔵 六弥勒 ななにおやくし はちにかんのん 七にお薬師 八に観音 くにはしせいの みだにょらい 九には勢至の 弥陀如来 あしくだいにち こくうぞう 阿閦大日 虚空蔵 |
『たなばた』 『七夕』 しちがつなぬかの たなばたに 七月七日の 七夕に おきからふねが うきてくる 沖から船が 浮きて来る たなばたさまの さきのりで 七夕様の 先乗りで あとにおきさき ただひとり 後にお妃 ただ独り なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 <不入斗> |
| 『ろくどう』 『六道』 ろくどうは ろくどうは 六道は 六道は つじにまよわば なむじぞう 辻に迷わば 南無地蔵 みちびきたまえ みだのじょうどへ 導き給え 弥陀の浄土へ なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 ふたつ 二つ ろくどうは ろくどうは 六道は 六道は いづるおうやは くらがらり いづるおうやは くらがらり なむあみだぶつを さきにたて 南無阿弥陀仏を 先にたて むあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 |
『さらさら』 『さらさら』 さらさらと さらさらと さらさらと さらさらと にわのいさご ふみわけて 庭の砂 踏分けて おてらまいりは さきのよのため お寺参りは 先の世の為 なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 ふたつ 二つ このてらに このてらに この寺に この寺に こがねのほとけが おたちやる 黄金の佛が お立ちやる そのやひかりで てらがかがやく そのや光で 寺が輝く なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 <不入斗> |
| 『しんけ』 『新家』 きみょうちょうらい このおんいえへ 帰命頂禮 この御家ヘ なんたらばんじょうが おたてやる なんたら番匠が お建てやる じゅうさんやと おあたごが 二十三夜と お愛宕が ばんじょうなさりて おたてやる 番匠なさりて お建てやる じゅうごやおつきが やねふきで 十五夜お月が 屋根葺きで みかづきさまが はりふきで 三日月様が 梁葺きで とらげみしまの しちくだけの とらげみしまの 七九だけの おほくだけて おしめやる おほくだけて おしめやる ほどなくおえも じょうじょして 程なくおえも じょうじょして めでたきものは わたまわし 目出度きものは わたまわし なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 このてらは このてらは この寺は この寺は しほうしらかべ すぎばんば 四方白壁 杉ばんば すぎとしびきを うえまぜて 杉と樒を 植え混ぜて しびきのはばめに はながさく 樒のはばめに 花が咲く はなじゃござらぬ みなろくじ 花じゃござらぬ みな六字 なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 |
『いしだて』 『石建て』 わがおやの わがおやの 我親の 我親の まんねんたもつ はかじるし 万年保つ 墓印 うえへねんごう きりつけて 上ヘ年号 切り付けて なかはかいみょう かきふらべ 中は戒名 書きふらべ したへれんげの ざをすえて 下ヘ蓮華の 座を据えて さてもみごとな はかじるし さても見事な 墓印 たてておがむ ものなれば 建てて拝む ものなれば すえはあんらく にぎやかに 末は安楽 賑やかに なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 <不入斗> |
| 『こうみょうへんじょう』 『光明遍照』 こうみょうへんじょう じゅっぽうせかい 光明遍照 十方世界 ねんぶつすぜう せっしゃふしゃ 念仏衆生 節射普射 せっしゃふしゃの こうめようの 節射普射の 光明の ねんずるところを てらすなり 念ずるところを 照らすなり こうめようの こうめようの 光明の 光明の ひかりかがやく みちなれば 光り輝く 道なれば ろくどうのつぢば ありやかにゆく 六道の辻ば ありやかに行く なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 |
えそげた 急げ? えそげただ えそげただ 急げただ 急げただ みのりのふねの いでぬまに 実りの舟の 出でぬ間に わがのりし わがのりし 我が乗りし 我が乗りし みのりのふねの みなしざお 実りの舟の みなし竿 さゝずとわたらへ みだのじょうどへ さゝずと渡らへ 弥陀の浄土へ なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 はやかわの はやかわの 早川の 早川の つながぬふねは とまれども 繋がぬ舟は 止まれども しするいのちは よもやとまらぬ 死する命は よもや止まらぬ なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 <勝間> |
| 『みだたのむ』 『弥陀頼む』 みだたのむ みだたのむ 弥陀頼む 弥陀頼む> ひとはあまよの ほしなれば 人は天世の 星なれば くもはれねど にしへこそゆく 雲晴れねど 西へこそゆく なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 みだたのむ みだたのむ 弥陀頼む 弥陀頼む らいせのことは みだたのむ 来世の事は 弥陀頼む ごくらくじょうどは とにもかくにも 極楽浄土は 兎にも角にも なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 |
『あげねんぶつ』 『あげ念佛』 われらがもうした おねんぶつは 我等が申した 御念佛は ほとけのために もうしおく 佛のために 申しおく うけとりたまえ これのおほとけ 受取り給え これのお佛 なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 おうじょうごくらく みだのじょうどへ 往生極楽 弥陀の浄土へ なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 <勝間> |
| 『わがおや』 『我親』 わがおやの 我親の たびのしょうぞく みもすれば 旅の装束 見もすれば こしよりしもは しろじたて 腰より下は 白仕立て こしよりかみは もんぎきょう 腰より上は もんぎきょう ずだとかんむり えりにかけ 頭陀と冠 襟に掛け ひらけしれんげを かさとして 開けし蓮華を 笠として つぼみしれんげを てにもちて 蕾みし蓮華を 手に持ちて なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 れんげのじくを つえとして 蓮華の軸を 杖として しゃかのみでしを さきとして 釈迦の御弟子を 先として すぐにじょうどへ まいるべし すぐに浄土へ 参るべし なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 |
『こどもねんぶつ』 『小供念佛』 あぶらひの あぶらひの 油灯の 油灯の とぼるまもなく うまれきて 灯る間もなく 生れきて おやをとはずに おやにとはれる 親をとはずに 親にとはれる なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 あさがおの あさがおの 朝顔の 朝顔の はなのうえなる つゆよりも 花の上なる 露よりも はかなきものは ひとのいのちかな はかなき物は 人の命かな なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 <勝間> |
| 『ねんきねんぶつ』 『年忌念佛』 うちならし うちならし 打ち鳴らし 打ち鳴らし かねのごしえを ゆめさめて 鉦のごしえを 夢醒めて あをのにじを きくぞうれしき あをの二字を 聞くぞ嬉しき なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 わがおやの わがおやの 我親の 我親の ほとけになるを ゆめにみて 佛になるを 夢に見て うれしながらも しぼるそでかな 嬉しながらも 絞る袖かな なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無)阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 |
『こどもねんぶつ』 『子供念佛』 きみょうちょうらい はなださん 帰命頂禮 花ださん はなのようなる こをもちて 花のようなる 子を持ちて むじょうのかぜに さそわれて 無常の風に 誘われて あまりわがこの かわいさに あまり我子の 可愛いさに はなだのてらにと てらまいり 花田の寺にと 寺参り てらのしょいんに こしをかけ 寺の書院に 腰をかけ つくづくおにわを ながむれば つくづくお庭を 眺むれば ひらけしなは ちりもせず 開けし花は 散りもせず つぼみしれんげが ちるごとく 蕾みし蓮華が 散る如く すなわちわがこも あのごとく すなわち我子も あの如く なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 <勝間> |
| 『ろくどう』 『六道』 ろくどうの ろくどうの 六道の 六道の つじにまよわば なむじぞう 辻に惑わば 南無地蔵 みちびきたまえ みだのじょうどへ 導き給え 弥陀の浄土へ なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 |
『おぼんねんぶつ』 『御盆念佛』 しちがつは しちがつは 七月は 七月は ほとけのために たかとうろう 佛のために 高燈籠 てんにおそれて ちゅうでかがやく 天におそれて 中で輝く なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 むさしのの むさしのの 武藏野の 武藏野の いろあるはなは おおけれど 色ある花は 多けれど なみだながすは みそはぎのはな 涙流すは みそはぎの花 なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 <勝間> |
| 『ひがんねんぶつ』 『彼岸念佛』 ありがたや ありがたや 有難や 有難や これのおしとげ ありがたや これのおしとげ 有難や こんにちひがんに あいあたり 今日彼岸に あい当たり ちゃくみのおんせき おそなえて 茶汲くみの御席 お供えて いざさらよりて おねんぶつ いざさらよりて 御念佛 なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 おひとげさまへの おみやげに おひとげさまへの 御土産に なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏> |
『ぎょうやねんぶつ』 『行屋念佛』 ありがたや ありがたや 有難や 有難や おぎょうやさまへは お行屋さまへは ぼんてん おたちやり 梵天 お立ちやり うちにはなゝよの しめをはり 内にはなゝよの 七五三をはり けさをむすんで えりにかけ 袈裟を結んで 襟に掛け ほうかんかぶりて みをきよめ 宝冠被りて 身を清め おくのおやまの ほととぎす 奥の御山の 時鳥 なにをめすやら こえがよい 何を召すやら 声が良い いちにかやのみ ににきのみ 一に茅の実 二に木の実 さんにしきびの はなをめす 三にしきびの 花を召す なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 <勝間> |
| 『はかいしをたてたねんぶつ』 『墓石を建た念佛』 ありがたや ありがたや 有難や 有難や こんにちたてたる はかいしは 今日建たる 墓石は まつだいまでの はかじるし 末代までの 墓標 うえにはいんごうを きりつけて 上には院号を 切り付けて したにはなまえを かきしるし 下には名前を 書き記し たてゝくどくを するひとは 建て功徳を する人は まつだいちょうじゃで くらすべし 末代長者で 暮すべし なむあみだぶつ なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 |
<勝間> |
| 『こうぼうだいしわさん』 『弘法大師和讃』 きみょうちょうらい へんじょうそん 帰命頂禮 遍照尊 ほうきごねんの みなづきに 宝亀五年の 六月に たまよるちょう さぬきがた 玉藻よるちょう 讃岐潟 びょうぶがうらに たんじょうし 屏風が浦に 誕生し おんとしななつの そのときに 御歳七つの 其の時に しゅじょうのために みをすてて 衆生の為に 身を捨てて いつつがたけに たつくもの 五が嶽に 立つ雲の たつるちかいぞ たのもしき 立つる誓いぞ 頼もしき なむだいし へんじょうそん 南無大師 遍照尊 ついにすなわち えんりゃくの 遂にすなわち 延暦の すえのとしなる さつきより の年なる 五月より ふじわらうじの かのうらと 藤原姓の 賀能等と もろこしぶねに のりをえて 遣唐船に 法を得て しるしをのこす ひともとの しるしを残す 一本の まつのひかりを よにひろく 松の光を 世に広く ひろめたまえる しゅうしをば 弘め給える 宗旨をば しんごんしゅうとぞ なづけたる 真言宗とぞ 名付けたる なむだいし へんじょうそん 南無大師 遍照尊 しんごんしゅうしの あんじんは 真言宗旨の 安心は じょうこんげこんの へだてなく 上根下の 隔てなく ぼんじょうふにと さだまれど 凡聖不二と 定まれど げこんにしめす いぎょうには 下根に示す 易行には ひとえにこうみょう しんごんを 偏に光明 真言を ぎょうじゅうざがに となうれば 行住座臥に 唱うれば しゅくしょういつしか きえはてゝ 宿障何時しか 消えはてゝ おうじょうじょうどと さだまりぬ 往生浄土と 定まりぬ なむだいし へんじょうそん 南無大師 遍照尊 ふてんにくしん じょうぶつの 不転肉身 成佛の みはありあけの こけのした 身は有明の 苔の下 ちかいはりゅうげの ひらくまで 誓は龍華の 開くまで にんどをてらす へんじょうそん 忍土を照らす 遍照尊 あおげばいよいよ たかのやま 仰げばいよいよ 高野山 くものうえびと しずのをも 雲の上人 賎の男も むすぶえにしの つたかづら 結ぶ縁の 蔦かづら すがりてのぼる うれしさよ 縋りて登る 嬉しさよ なむだいし へんじょうそん 南無大師 遍照尊 むかしくにじゅう おおひでり 昔国中 大旱魃 のやまのくさき みなかれぬ 野山の草木 皆枯れぬ そのときだいし ちょくをうけ 其の時大師 勅を受け しんぜんえんに あまごいし 神泉苑に 雨乞いし かんろのあめを ふらしては 甘露の雨を 降らしては ごこくのたねを むすばしめ 五穀の種を 結ばしめ くにのうれいを のぞきたる 国の患を 除きたる いさおはいまに かくれなし 功は今に 隠れ無し なむだいし へんじょうそん 南無大師 遍照尊 なむだいじだいひ へんじょうそん 南無大慈大悲 遍照尊 しゅうじうじゅうざい ごぎゃくしょうめつ 種々重罪 五逆消滅 じたびょうどう そくしんじょうぶつ 自他平等 即身成佛 |
『こうぼうだいし』 弘法大師 ありがたや 有難や たかののやまの いわかげに 高野の山の 岩陰に だいしはいまに おわします 大師は今に 居わします |
| 『こうきょうだいし』 『興教大師』 ゆめのうち ゆめもうつゝの ゆめなれば 夢の内 夢も現の 夢なれば さめてはゆめも うつゝとぞしれ 醒めては夢も 現とぞ知れ <勝間> |
|
| 『ぜんこうじ』 『善光寺』 ありがたや 有難)や かねのすだれを まきあげて 金の簾を 巻き上げて ねんぶつこえを きくぞうれしき 念佛声を 聞くぞ嬉しき みはこゝに 身はこゝに こころしなのの ぜんこうじ 心信濃の 善光寺 みちびきたまえ みだのじょうどへ 導き給え 弥陀の浄土へ |
|
| 『りゅうしょういん』 (下の寺) 『龍性院』 ごくらくの 極楽の たからのいけを おもえたゞ 寶の池を 思えたゞ こがねのいずみ すみたたえたる 黄金の泉) 澄み湛えたる <勝間> |
|
| 『まんこういん』 (萩作) 『満光院』( ごくらくの 極楽の みだのじょうどへ ゆきたくば 弥陀の浄土へ 行きたくば なむあみだぶつ くちぐせにせよ 南無阿弥陀仏 口癖にせよ |
|
| 『じぞういん』 (葉木) 『地蔵院』 むつのちり いつつのやしろ あらわして 六つの塵 五つの社 顕して ふるきにいだの かみのたのしみ 古き仁井田の 神の楽しみ |
|
| 『ほうせんじ』 (下の寺) 『法泉寺』 ながむれば 眺(なが)むれば つきしろたえの よわなれや 月白妙の 夜半なれや たゞくろたにに すみぞめのそで たゞくろたにに 墨染の袖 <勝間> |
|
| 『じんしょうじ』 (上の寺) 『神照寺』 いくさには 戦には かつまときけば ぼんのうの 勝間と聞けば 煩悩の つみはほろびん ちえのじりに 罪は滅びん 知恵の鏃に とらやくし とら薬師 せんりのみちを ひとすじに 千里の道を 一筋に みちびきたまえ みだのじょうどへ 導き給え 弥陀の浄土へ |
|
| 『かさもりじ』 『笠森寺』 だいひなる 大悲なる かさもりでらの みほとけに 笠森寺の 御佛に くすのひかりが よもにかがやく 楠の光が 四方に輝く ひはくるゝ 日は暮るゝ あめはふるのの みちすがら 雨は降る野の 道すがら かかるたびじを たのむかさもり かかる旅路を 頼む笠森 うきにふる うきに降る なみだのそでに ぬれるとぞ 涙の袖に 濡れるとぞ きょうはかさもり たずねきにけり 今日は笠森 尋ね来にけり <勝間> |
|
| 『じゅうさんぶつ』 『十三佛」 われらがもうしたる おねんぶつは 我等が申したる お念佛は ろくまんろくせん ろくじぞう 六万六千 六地蔵 じゅうまんおくの みだたのむ 十万億の 弥陀頼む たのみもうすよ じゅうさんぶつ 頼み申すよ 十三佛 ごくらくじょうどの まんなかに 極楽浄土の 真ん中に おふどうさまが おたちやり お不動様が お立ちやり とにもかくにも わがみをば 兎にも角にも 我身をば おふどうさまに まかせおく お不動様に 任せおく なむあみだぶつ 南無阿弥陀仏 |
|
|
『だいしさま』 |