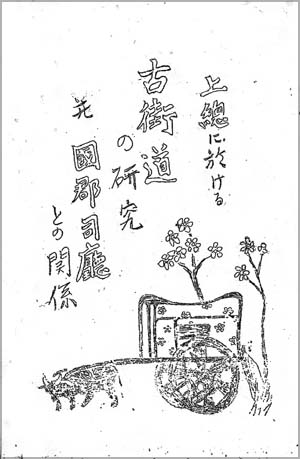 上總に於ける云々と言ひながら西上總の資料多くして東上總の資料に少なきは古街道幹線との関係上自然の成行なれども亦未調査に属するもの少なからず此等は他日増補する所あらんとす。幸に之を諒せられよ 又是に関係の資料御高説とも御示教を賜はらば幸甚。
上總に於ける云々と言ひながら西上總の資料多くして東上總の資料に少なきは古街道幹線との関係上自然の成行なれども亦未調査に属するもの少なからず此等は他日増補する所あらんとす。幸に之を諒せられよ 又是に関係の資料御高説とも御示教を賜はらば幸甚。昭和七年一月 小熊吉蔵
鎌倉街道と大街道に就て
◎鎌倉街道研究の動機
明治四十年頃東京帝國大學圖書館内に所蔵の元内務省地理局が明治十八九年頃全國に向って大日本國誌編纂の目的を以て其の資料を徴収されき。
其の資料の中上總に関する部を借覧する事を得たり。中に君津郡波岡村元中烏田村字曲り坂に鎌倉道の示道標の在ることを發見し珍らしく思ひたり。歸郷するや閑を得ては屢々實地踏査を試みたるに嘗て見る所を聊か異なる点なかりき。
鎌倉道の上にあるは慥に北と云ふ字なるが故に示道碑所在地より北に當りて踏査せしに木更津に向ひたるが如くなりき。其後根形村役場に就て字名を調査したるに元野田村にて『鎌倉街道』と言ふあり、平岡村役場に到りしに仝村川原井に字『鎌倉通り』と言ふ所ありき。
右二箇所を基点として踏査を試みたるに右『鎌倉通り』は君津郡と市原郡の郡界に當り戸田村中高根及姉崎町の内椎津新田の飛地に接し此所より西に向って現今の縣道の如き古道にて大体市原郡と君津郡の郡界をなし西根形村に入り東戸田村に入るものありて今尚鎌倉街道と呼び居ることを知れり。
鎌倉街道に沿ひたる地名を挙ぐれば北は姉崎町椎津新田(飛地)、深城、天羽田、君津郡長浦村蔵波、根形村野田にして南に沿ひたる地を挙ぐれば、平岡村川原井、上泉、下泉、及根形村岩井、大曽根、三ツ作是なり。
何れも現今尚道路として使用しつゝあれども往古の状態は略之を失ひたるが如し。所によりては道幅十間位もあらんかと思はるゝ所あり、土手が道路の両側にあり其の上に大木の並木をなせるものありしを想像せしむべき所もあり。又之れに沿ひて古櫻の樹齢数百年ならんかと思はるゝが花時は今尚爛熳たるものあり。
之れに沿ひて古墳あり、白幡森あり傾城窪と称する特殊の地もあり、鎌倉時代に守護地頭等の人々が家来を率ゐて鎌倉に往復せし昔を偲ばしむ。
扨此鎌倉街道は鎌倉に到らんには之より如何にしたるか。根形村飯富の飯富新田と称する地に白幡森あり。此邊を通過したるが如く其れより中郷村清川村を經て木更津に向ひたるものの如くにして果して然るや否や未だ詳にすることを得ざりしなり。
木更津町貝淵の人伊藤亀之助の調査に依り貝淵の南方字『渡海面』と称する地あるを知り踏査を試みしに前述中烏田示道碑の示せるものも平岡根形方面より来れる鎌倉街道も二つながら此の渡海面より乗船して彼地に赴くことを確めたり。
木更津より乗船して何れの地に上陸せしかは『廻國雑記』の示す所によりて知ることを得たり。
前略『浦川の湊といへる所に至る ここは昔頼朝卿の鎌倉に住ませ給ふとき金澤榎戸浦河とて三つの湊なりけるとかや 云々』
之に依りて地形上木更津より渡海せんには金澤か榎戸に着陸すべきを思ふ。
而して茲に傍證となるべき一話あり。木更津町の北端に祀れる吾妻神社は昔金澤の稱名寺が別當たりし事ありと、されば金澤より上陸したるにて彼の朝比奈堀切を通りて鎌倉に入りしことを知られたり。
先年内務省地理局員が彼の鎌倉街道の示道碑を發見せし當時の記事に依れば建久年間建てしものとせり。されば平廣常讒に逢ひて殺されし後の事にて足利義兼國司たりし時の事にて鎌倉街道の出来たると猶同時の事なるべし。
中烏田示道碑を起点とせる鎌倉道も戸田村より根形村に至る鎌倉街道も何れも木更津より渡海して金澤に到しなるべく其の延長線上にして同様の名称を負へるものもあるべく又支線も若干あるべく前記二道は其の幹線と見るべきものなり。
畢竟源頼朝鎌倉幕府創立の當初中央なる鎌倉に地方の守護地頭等を連絡すべき街道は即ち是れにして國府は尚存在したれば國府を経由せるものの如し。
◎大街道と國府郡家の所在に就て。
鎌倉街道と大街道とは所によりては甚だ紛らはしきものなきにしもあらざれども素より性質を異にし 時代に於ても同じく古昔の街道ながら大に先後あるものなれば之れを大観すれば極めて明瞭となるべし。
今日鎌倉街道として明瞭なる平岡村 姉ケ崎町 戸田村三町村の境界点に近き所に於て鎌倉街道に接續して戸田村の地籍内に字『大街道』と呼ばるゝ地あり。就て見るに鎌倉街道より分岐して往古の大街道の遺蹟と見るべき道路ありて北方に向って折れ、和名抄に所謂『海上郡』の郡家所在の『小折』に到るべく、亦直に上總國府所在地なる市原郡市原村惣社にも到るべし。
之れが鎌倉街道の延長ならんには大街道という別の名のよぶべき筈なし。
又鎌倉街道中平岡村根形村長浦村三村の境界点の附近の或る地点より分岐して斜めに西南に向ひ五六十度の角度をなす古道ありき。今や全く遺蹟を失ひたれど二三十年以前までは鎌倉街道に比すべき古昔の街道あり。道路の両側に土手あり其の上には古松並び立ちたるものの如くなりき。此古道の何と名づけたるやは明ならざれども大体前記大街道の延長と見るべきものにして或る地点にては鎌倉街道と一致し居れど此れは甚だ稀にして多くの場合は全然方向を異にせり。
大街道とは甲の國府より乙の國府に到る昔の國道にして其の中間各郡の郡家所在地を通過するを常とせり。
されば我千葉縣にありては北の方下總國府の所在地たる東葛飾郡市川町國府䑓より南は千葉郡の郡家所在地千葉を經て上總國府所在地市原郡市原村能満に到り次第に南に向ひ海上郡の郡家所在地なる海上村小折を經て少しく東の方に迂廻し海上村の安須高坂を経て戸田村中高根の七日市場の西方を南に向ひ字大街道にて鎌倉街道に合し暫らく一致して根形村の東邊大曽根三ツ作の境界線に依りて鎌倉街道と分岐し通称『馬坂』を下り望陀郡の郡家所在地なる中郷村下望陀に到り更に南して小櫃川を渡り中川村大鳥居を貫き中川村清川村富岡村鎌足村の境界線に接近して略々並行して南へ南へと進みて彼の有名なる高倉観音の北方『あびる』と稱する地に到る。是れは和名抄に所謂『畔蒜郡』の郡家所在の地にして是れより少しく西南に向ひ中村大井を過ぎて小糸川を渡り中島を經て周南村の常代の北邊を西に向ひ貞元村郡春日神社の附近に到る。(此道は後世高倉道と呼ぶものなり。)之れ即ち周准郡の郡家所在地にして古へは『いか江じり』と呼びしを郡家所在の地なりしを記念するため『郡村』と呼びたるなり。
其れより尚南に向ひ周南村吉野村佐貫町の境界線に近く略々並行して大貫町小久保岩入なる通称『古道』を南に越え佐貫町北上を貫きて迎原に到り牛蒡谷に出で染川の上流を渡りて花香谷より西に向ひて小山脈の山嶺を湊町岩坂に到り八坂神社の東より坂を下り南に赴き數馬と稱する地を過ぎて湊川を渡り天神山村不入斗なる六所神社の附近一町目と呼べる地に到る。此地は古昔『天羽』と呼べる地にして之れより南に向ひ今の相川の北邊近き山中に天羽城の遺趾の存するあり。是れ鎌倉幕府の初に當りて舊領安堵を與へられたる平直胤(廣常の弟)の天羽莊司として居りし地なるべし。
天羽郡内天羽と稱せる地他に未だこれあるを聞かず。之れを以て此の付近を天羽と呼べるものなることを推定せるものにして天羽郡家所在地亦この附近にあるべきなり。(尚後の研究者を俟つ)
此地より梨澤に入り南へ南へと進み天神山村と駒山村の境界線に沿ひて遂に房州に入る。保田町佐久間村の東端に近く平群村伊豫岳の北方より西に向ひ川上に到る。(此地は川上驛の在りし所)此の付近に平群郡家の所在地あるべきも未だ之を詳にせず。それより尚南に向ひ滝田村を過ぎて安房國府の所在地なる國府村府中に到る。以上通過せる下總國府より上總國府に到りそれより海上 望陀 畔蒜 周准 天羽各郡の郡家所在地を經て安房の國府に到るは是れ即ち王朝時代大化の改新の頃より始まり鎌倉幕府當初の頃まで約六百年の永き年月續きて交通道路の幹線となり文化流通の大動脈管たる役目を畫しつゝありし大街道即ち是れなり
是れを以て大街道の沿道近く古墳群あり又市場といふ地名多し。是れ商業史の所謂物々交換をもなし各種生産物其他外國より輸入せる品物までも二日、五日、七日、八日、九日、十日、廿日等と日を期して此地に集まり郡司廳の掛りの役人出張して監督の下に正午太鼓を打ちて合圖となし開市し、日沒又太鼓の合圖に依りて閉市したりしなり。されば各種の農商工集まるのみならず、僧侶の布教各種の宣傳等の事も行はれしなるべく其の繁盛思ひやらるゝなり。
『傾城町』或は『傾城久保』など呼ぶ地名も亦其の沿道にあり。是れは古昔旅館の發達せざる時代には沿道の寺院民家に宿し、或は木陰に野宿するさへあり。不便を極めたる當時にありて、旅人の旅情を慰めたるものは旅宿に先ちて遊女町あるのみなりき。其の遺蹟なるべし、神社佛閣の有名なるもの古きものも亦多く、城趾も其の附近に多きを見、市街地の發達も是れに基けるもの多かるべし。
特に鎌倉街道に添ひては白幡森、白幡神社等多きを見るは是れ源頼朝を祀れる社の趾なるべし。
◎源頼朝が治承四年石橋山の戦いに敗れ安房に遁れやがて安房を出でて上總を經て下總に入り武蔵を過ぎて終に相模の鎌倉に入りて茲に幕府を建設せるは極めて明瞭普及の事柄なり。
鎌倉幕府建設の當初建久年間に鎌倉街道を設けたりと稱せり。即ち中央の幕府と地方の國々にある守護地頭と連絡を取り、いざ鎌倉と聞けば各地の武士はなるべく徑捷の途を取りて上鎌したるにて彼の謡曲『鉢の木』に見ゆる如く、武士の鎌倉上りの盛況思ひやらるべし。
現今の交通を車の時代とすれば此の頃は馬の時代にして川を渡るには多く橋無く徒渉多く、極めて枢要の地には稀に橋を架したりと見へて大橋等の地名の存するものも無きにあらざれども多くは之れ無く徒渉せざれば馬に乗りて渉り、荷物も馬上によること多かりき。されば大街道には驛傳の制あり、國郡司廰には必ず若干の傳馬を備へ其他驛ありて凡五里毎に一驛の標準に之を置き公人官人の乗馬駄馬の用に充てたり。馬立、馬坂、厩尻、大厩等馬に縁ある地名の此等街道附近に多きは是の故なり。(此外に牛馬放牧の地ありしは無論なり。)
前述頼朝の上總通過は安房を出で上總の西邊を通りて下總に入りしなれば、南より北に入る方向にして鎌倉街道は東の上總の地に在る人々が西の方内海を渡りて鎌倉に入る東西の方向を取るものなれば南北と東西の相異あり。又彼れは敗残の一武将の通過にして此れは堂々幕府の征夷大将軍たる頼朝卿の許に到らんとする守護地頭等の武士を始め農工商各民衆の實業上の交通路なれば其の性質に大なる差異あるなり。
◎上總に於ける古昔交通の変遷
大化の改新に於ける國郡制の實施の當初に於て東海道と稱する國々の中にて武蔵國は東山道に属しけるが故に東海道諸國を連ぬる大街道即ち東海道の本道は随て武蔵に入らず相模より海を渡りて對岸地なる君津郡富津町の南なる大貫湾に上陸したるなるべし。(地形上より)
而して周准郡々家所在貞元村郡に到り、それより順次各郡家所在を經過して上總の國府に到り、更に下総の國府を經て終に常陸の國府に到りしなり。然るに光仁天皇の御宇となり、即ち奈良朝の末に到りて東山道に属してゐた武蔵が東海道の仲間入りをしたるに依り随て東海道の本道も相模より武蔵を經て下總に到り、下總の國府より上總の國府に到り更に南下して安房國府に到りしなり。
上總と言ひ下總と言ふ此の名稱より見るも之れを證することを得べし。
房總の地始めは『總の國』と言ひけるを後分ちて上下の二つとせり、上下の意味は今日も昔も同じく、帝都所在地に近きは上にして遠きは下なり。現今東京に帝都あるなれば今日總を分ちて上下の二つとなすなれば北總が上總にして、南總は却って下總となるべき筈なれど、その名の然らざるは東海道の本道に海路を經たるものと陸路に依りしものとの差が生じたるものにして奈良朝以前の上總は海路直に上陸し西方文化輸入の門戸に當れるより此方面の文化は多少早かるべきも、東海道が支線の如きに到りては衰運に赴きたり。此時に當りて鎌倉に幕府起り一葦海水を隔てたる上總は又海路鎌倉に入る要を占めたるがため此時代には未だ甚しき悪影響を見るに至らざりしなり。
交通道路の文化に影響する大なるは古今其趣を同しふすと謂ふべし。