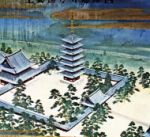 『日本で金が初めて発見されたのは、東大寺の大仏が作られてた奈良時代で、その発見者は市原の出身であった。』なんてご存知でしたか!?
『日本で金が初めて発見されたのは、東大寺の大仏が作られてた奈良時代で、その発見者は市原の出身であった。』なんてご存知でしたか!?その人の名は『丈部大麻呂(はせつかべおおまろ)』、聞いたことが無い名前ですが谷島一馬氏(千葉県文化財保護協会評議委員、島野在住)の研究により、大麻呂は上総(市原)の人である事が究明されました。
これからは『日本で初めての金の発見者、上総の人 丈部大麻呂(はせつかべおおまろ)』を覚えてください。
図は丈部大麻呂当時の上総国分寺の復元図
三井石油化学工業(株)千葉工場社内報『ちぐさ』に掲載された谷島氏の記事を紹介します。
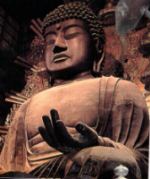 今から千二百年程前、聖武天皇の発願に依り、国中連君麻呂等によって五丈三尺五寸(約十五米)という金銅製盧舎那仏・奈良東大寺大仏が鋳造された。 この大仏の完成を前にして聖武天皇は塗金用の金が大巾に不足し、八方手を盡しても補充出来ず苦慮していたところ日本には産出されないと思われていた黄金が陸奥国司百済王(くだらのこにしき)敬福より陸奥国小田郡から産出された黄金九〇〇両(十二.六㎏)を献納して来た。塗金総量四千百八十七両一分四銖(約五八.五㎏)の内五分ノ一相当の黄金が献納された事になる。 聖武天皇はいたく感激され、これを慶祝して年号を「天平感宝」と改元され、天平二十一年四月朔、東大寺大仏の前に行幸され、黄金発見を寿く史上例のない長文の宜命(詔勅)を奏上された。
今から千二百年程前、聖武天皇の発願に依り、国中連君麻呂等によって五丈三尺五寸(約十五米)という金銅製盧舎那仏・奈良東大寺大仏が鋳造された。 この大仏の完成を前にして聖武天皇は塗金用の金が大巾に不足し、八方手を盡しても補充出来ず苦慮していたところ日本には産出されないと思われていた黄金が陸奥国司百済王(くだらのこにしき)敬福より陸奥国小田郡から産出された黄金九〇〇両(十二.六㎏)を献納して来た。塗金総量四千百八十七両一分四銖(約五八.五㎏)の内五分ノ一相当の黄金が献納された事になる。 聖武天皇はいたく感激され、これを慶祝して年号を「天平感宝」と改元され、天平二十一年四月朔、東大寺大仏の前に行幸され、黄金発見を寿く史上例のない長文の宜命(詔勅)を奏上された。この陸奥国に於ける金採掘者は、日本の正史である「続日本紀」に「獲金人上総国人丈部大麻呂並従五位下」と記すのみであるが、彼の本貫地は市原であると考えられる。それは上総国司であった百済王敬福が、天平十八年九月陸奥国司として陸奥に赴く際に、上総国府の小壮武人であった丈部大麻呂を同国に伴って行ったものと思われ、市原の人物とみても大過ないと考えられる。これに関しては、涌谷町元議会議員・高橋高志氏や京都文京短大名誉教授・中山修一氏等の古代史研究家も一致した見解である。
 また、東大寺に貢納された黄金の産地は、現宮城県遠田郡涌谷町黄金山・式内社戸黄金山神社附近である。
また、東大寺に貢納された黄金の産地は、現宮城県遠田郡涌谷町黄金山・式内社戸黄金山神社附近である。大伴家持は「陸奥国より金(くがね)を出せる詔書を賀く」和歌に、「万葉集第十八」
海行ば水漬く屍
山行ば草生す(くさむす)屍
大君の辺にこそ死なめ
顧みは為じ
と詠んだ。
この歌は吾々意識の中に鎮魂の歌のイメージが強いが、金発見に対する歓喜の歌であり、大伴氏が天皇に忠誠を誓った決意表明の歌であるが、丈部大麻呂の黄金発見に依って顕現した歌であることに注目したい。
以下 略
詳しくは『丈部大麻呂の研究』谷島一馬氏(市原地方研究10号 市原市教育委員会発行)をご覧下さい。
『黄金山神社』の写真は涌谷町HPより、涌谷町HPへは『LINK』から